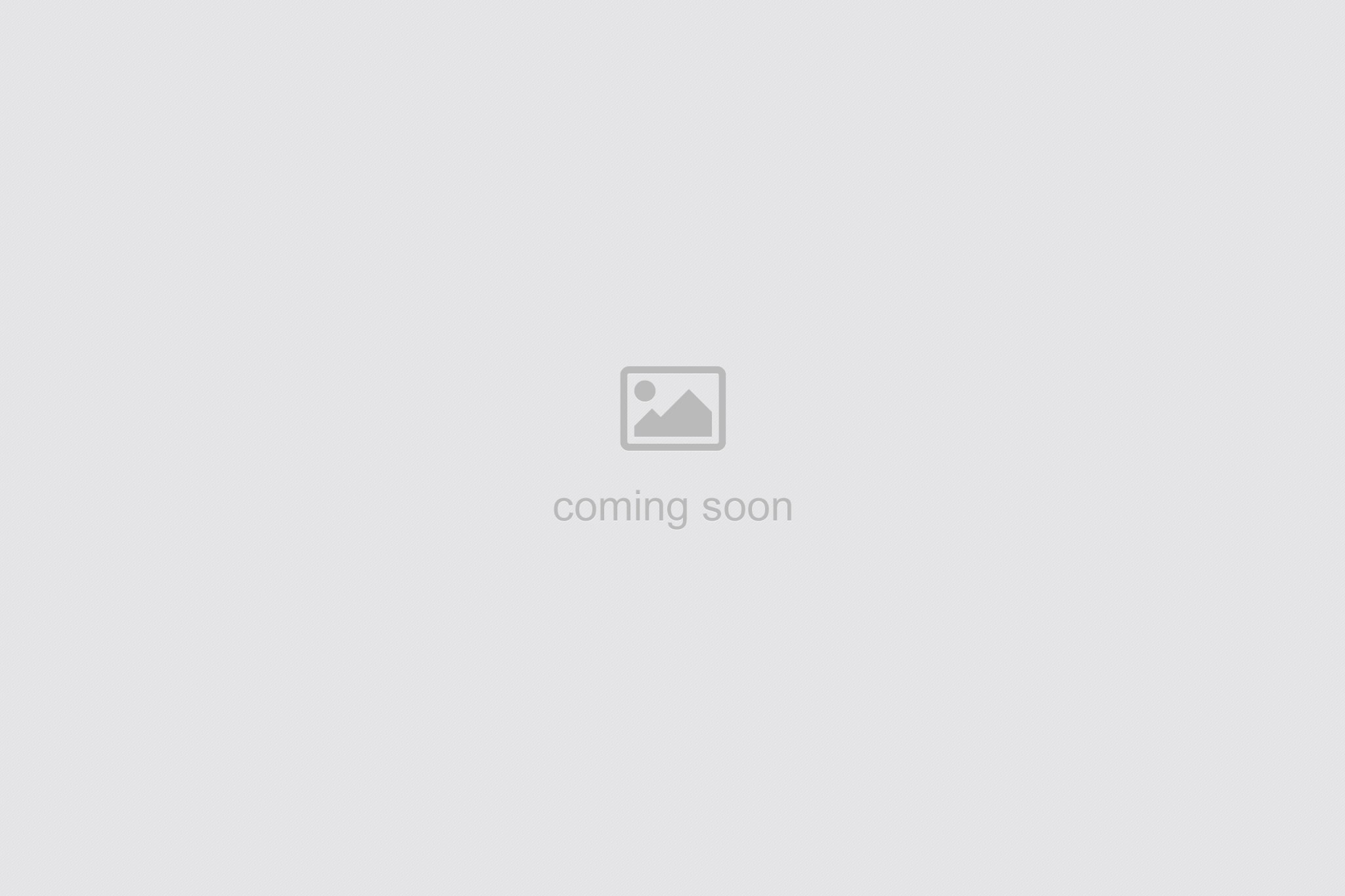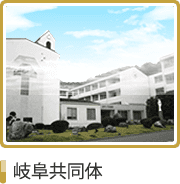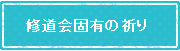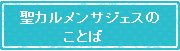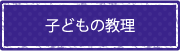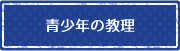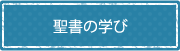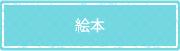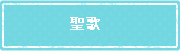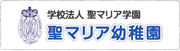聖書の学び資料
イエスの不可解な行動
マルコによる福音 11章 1-14節
時々、聖書を読んでいてイエス様の行動が理解できないことがあります。弟子たちが驚く場面も聖書には描かれていますが、その一つが、エルサレムへ向かうということでした。イエス様と弟子たちがまだガリラヤ周辺で活動していた時、ファリサイ派の人々や律法学者たちがエルサレムから来て、イエス様に議論を仕掛けたりしていました。そして、掟よりも愛を大事にするイエス様に反感を抱き、イエス様を殺そうとまでしていたのにもかかわらず、その律法学者たちのいるエルサレムに行くということは、死に行くようなものです。弟子たちは、イエス様がなぜエルサレムへと向かうのか理解できませんでした。弟子たちはイエス様を、ローマからの解放に導く指導者と思っていたため、ここで死んでもらっては困るのです。そんな中、今日は、いよいよエルサレムの街に入って行くという場面を読みました。理解できないことの中には、イエス様がロバに乗ってエルサレムに入ったということもあげられます。ロバは、ローマからの独立のために戦うためのものではありません。戦うためなら馬に乗ります。人々は、働くため、荷物を運ぶためにロバを使っていました。日常、つまり平和を象徴しています。ロバを見ると、「平和ボケ」をイメージしてしまいます。イエス様はロバに乗ることで、戦うのではなく平和をもたらそうとしていることを象徴しています。この場面から今日は、改めて平和について考えてみたいと思います。日本は平和の国と言われますが、戦争がないということだけが平和なのでしょうか。私たちの身近に、人との関わりの中に、あるいは私たちの心の中に、平和があるでしょうか。そして、これから殺されることが分かっていながら「平和」を強調しているイエス様の心の中は、どんなだったでしょうか。想像してみましょう。
イエス様は、エルサレムに入ってから様々なことをなさいましたが、マルコの11章には、不思議な行動ばかりが描かれています。いちじくの木を呪う事から始まって、神殿で暴れます。神殿を清めるため、祈りの場である神殿を大切にするために、イエス様はこのような行動を取られたのだとよく言われますが、優しいイエス様、弱い立場の人々を受け入れてくださるイエス様をイメージしている私たちには、このような行動を見せ付けられては、やはり疑問に思ってしまいます。遠くからエルサレム巡礼に来る人々は、神殿に捧げる鳩や羊を持って旅をすることは困難です。神殿での商売は、このような人々のために販売している物で、神殿で商売をしていた人々は多くの場合、それで生計を立てていた人々です。その現状を見れば見るほど、イエス様の行動の理由が分からなくなります。力のある人は神殿の中で商売をし、貧しい人、弱い立場の人は、神殿の外で物を売っていました。ですから、このような差別を嫌ってした行動であるとも考えられますが、やはり疑問が残ります。いちじくの木を呪う話を見てみましょう。これは、聖書学者でも解釈が分かれます。いちじくの季節でもないのに実がないことを呪うなんて、言語道断。常識ではありません。それなのに、「いちじくの季節ではなかったからである」とわざわざ注釈を入れたということは、何かを象徴した話だということです。「実をつけないいちじく」つまり、神様にとって良いものである「実」を付けていない木とは、神様の好む行動をしないイスラエルの人々です。その象徴がファリサイ派や律法学者、祭司たちのものとなってしまった神殿です。いちじくの木を呪うのと、神殿で暴れるのと、同じことを象徴しています。いちじくの木はその後枯れましたが、実際、ユダヤ戦争によって神殿も、紀元70年には破壊されてしまいます。このように見ると、やはり神殿での商売は、神様にとって好ましくないのだということが分かります。神聖な場所は神聖な場所であることをわきまえなければならないのでしょう。現代のお聖堂を神聖な場所として、敬意を示しましょう。何かの機会で教会の近くを通ったら、用事がなくても聖堂をのぞいてイエス様に挨拶する、ということをしてみてください。1週間に一度でも、ミサの前にでも、聖堂にしばらく座って、静かに祈ることもしてみてください。イエス様に対する信仰が深まるのを感じるでしょう。